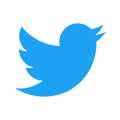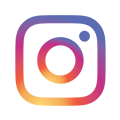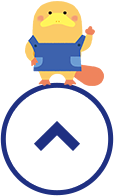子どもは叱っていいの?叱らないほうがいいの?

現代の育児の中で「叱らない育児」といった言葉を見聞きしたことがある人もいるのではないでしょうか。
子どもに対して叱って良いのか叱らないほうが良いのか、保育中にも悩むことがあるかもしれません。
今回は子どもに叱って良いのかどうか、叱るならばどういった注意点があるのかわかりやすく説明していきます。
子どもは叱っても良いの?
子どもは叱っても良いのか悪いのか、結論としては「場面によっては叱ることが大切」というのが保育の中の共通認識。
とはいえ、保育を行う中で「子どもの主体性を大切にする」ということは絶対忘れてはいけません。
主体性を大切にするということは、悪いことをしても叱らないということではなく、危険行為や人としてしてはいけないことをした時は何が悪かったのかお話しする必要があります。
例えば、大きな怪我や事故に繋がるような行動をしたとき、喧嘩や言い合いなどで相手に怪我をさせたとき、人を傷つけるような言葉を使ったとき、ルールやマナーを無視しているときなどに、子どもに対して何がいけないのか、どうしたら良かったのか、しっかりと伝えなくてはいけません。
子どもを叱る時の注意点
子どもを叱るべき場面があった時は、以下のことに注意してお話をするようにしましょう。
叱るべき場面は思わぬタイミングで訪れることが多く、臨機応変な対応や声掛けが大切になってきます。
・感情的にならない
子どもを叱る時に大切なのは、感情的にならないことです。
よく「叱る」と「怒る」は違うと言われていますが、怒るというのは感情的に怒りをぶつけていることを指します。
イライラの感情をぶつけるのではなく、何が悪いのか・どうすべきだったかを冷静に伝えるようにしましょう。
・怒鳴らない
叱る上で1番大切といっても過言ではないのが、怒鳴らないことです。
怒鳴ってしまうのは感情的になっている証拠で、大きな声を出して伝えても、子どもは大きな声を出された驚きと迫力で何が悪かったのか理解することができません。
「叱る時は冷静に」と常に意識しておくことが大切です。
・子どもに寄り添う
子どもの喧嘩の仲裁をするときは、無理に謝らせず子ども自ら自分が悪かったことに納得して「ごめんね」ができるような声掛けや環境を整えるましょう。
また、許すか許さないかは子ども自身に託すことも大切です。
嫌なことをされた側の子どもが「ごめんね」と言われてもすぐに許す気持ちになれなかったら、「いいよ」ではなく「わかったよ」と返事をしても良いということを教えていくと良いでしょう。
・両者の意見を聞き、気持ちを受け止める
喧嘩の仲裁では、両者の意見をしっかり聞きましょう。
幼い子どもたちの喧嘩はお互いに聞き間違いや言い間違い、勘違いしている部分もあるので、ゆっくり話ができる環境を整えてからお話を聞き、気持ちを受け止めることが大切です。
・どうしたら良いかを一緒に考える
子どもを叱る時は、何がダメだったか、どうして悪かったのかという話をした後に「じゃあ、どうすれば良かったのかな?」と一緒に考え、次の行動に活かせるような声掛けが必須となります。
子どもが分からない場合は、「先生は〇〇してくれたら嬉しいな」「困ったら先生やお友達に声を掛けてね」など解決策を考え伝えることが大事です。
まとめ
子どもを叱ることについてのお話をしてきました。
現役の保育士でも子どもを叱る時の対応は難しく、声掛けもどうしたら良いのか悩む人も多くいます。
叱る場面のポイントをしっかり押さえ、感情的にならず冷静にわかりやすく伝え、解決策を見出せるよう最後まで対応することが大切なので、落ち着いて対処できるよう日々考えていきましょう。